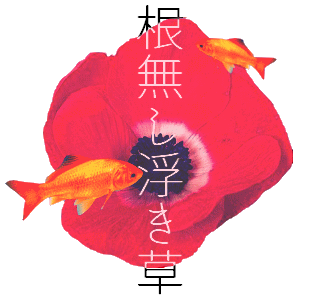
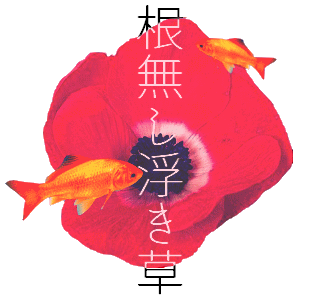
とある本丸のやや隅のほうにある、満開の桜の大木に近い小さな一室。気持ちがいいほど全開にされた障子から、遠くに春の穏やかな青空を望むことができる。
不意に強い風が吹き、薄紅の花びらが縁側を越えて部屋の中へと舞い込んだ。ここに堀川がいたのなら、「掃除が大変…」と肩を落としていたことだろう。
そんな中でも能天気に寝こけているのは、この本丸の主ことだった。
持ち物の少ないの部屋はがらんとしていて、たまに使う時はこうして寝床になる程度だ。
ふと、の上にふっと影が差す。
「…」
宗三はぐうぐうと眠る黙ってを見下ろすと、振り返って花を散らす樹木を見上げた。それからもう一度背後にいるを見直して、らしからぬほど深い溜息をつく。
一歩足を踏み入れて、宗三は畳の上に無数に散らばった花びらを追い出すのを早々に諦めた。
の平和ぼけした寝顔を見ていると、苛立つような、落ち着かない気持ちになる。そんな心とは裏腹に、宗三は障子を静かに締め切った。
さて、と宗三は目を伏せる。こうしてを訪ねたのにはなんの意味もなかったし、なんなら嫌味のひとつでも言ってさっさと退散しようと思っていたのに、当の本人は夢の中で肩透かしを食らった気分だ。
宗三はそっとしゃがみこんで頬杖をつくと、涎を垂らして寝ているの顔を覗き込んだ。そういえば、こんなに近くでこの人をまじまじと見たのは初めてだと思った。
陽にさらされ色落ちしてぱさついた髪は、綿毛のようにふわふわしている。頬には赤い畳のあとがくっきりついていた。「(…ぶさいく)」どことなく不服で、その頬をひっぱたいてやりたくなる。
「…」
けれども、伸ばされた宗三の手は、ただためらいがちにの髪を撫でるだけだった。
には、放浪癖があった。
通信機器の類が発達したの時代では、そこに肉体がなくとも、意志やその他もろもろの伝達は容易に行ってしまえる。いざとなれば、離れた場所だろうと一瞬で行き来することもできる。意思は本丸に、体は自由に放浪。それがという、一風変わった審神者だった。
宗三が初めてこの本丸にやってきた時、顕現した宗三が自らにまつわる皮肉を言い終わらぬうちに、は形だけの歓迎会を終えてさっさと外へ出て行ってしまった。あまりの事態に理解がついていかず取り残された宗三といえば、こんな粗末に扱われたのは初めてだとすこし苛立ったのを覚えている。
戸惑う宗三をよそに、他の刀剣たちは皆一様に気にしないといった。別に仕事はしてるんだからと。近侍の陸奥守なんかは、張り切ってを送り出す始末だった。かといって、主不在でも本丸は無法地帯ということもない。あの加州や大和守ですら、「絶対帰ってくるから大丈夫」と気丈だった。
そうやって自分の気を惹こうとしているのか?自分は理解があるとでも言いたいのか?
宗三がどれだけ疑っても、は気づけばふらりと消えてしまう。たったわずか会える時間に、宗三はなぜだか意固地になっての粗探しをした。
障子紙を通して春の陽光がくすむ。薄暗い室内は籠もりがちだった宗三に馴染み深く、少しだけ落ち着いた。伸びた己の影にほう、と安堵の息のようなものを吐いてしまってから、宗三はすぐさま自己嫌悪した。まるで、好き好んで籠の中にいるようじゃないか…。
この本丸に来て、という風変わりな主に出会って、宗三は自分のことを考えなければならない時間が増えた。
あんなに望んでいた戦いにも出してもらえる。見世物のように扱われることもなく、何なら何かを口うるさく言われるようなことだってない。刀を全うできて、きっと願ってもない“自由”だったはずだ。それなのに、なぜ、どこか満たされないでいるのか。
宗三のすぐ後にやってきた物吉が、へなぜ旅するのかと問いかけていたのを、偶然盗み聞きしたことがある。その時が「…自分がわからない気がするから。…自分が何者か知りたいから?」とやや困ったように答えていたのが、宗三の中で印象深く残っている。
多分きっとあの時、宗三は、に自分を重ねた。
骨肉を得て、口もきけないただの刀だった時よりもやれることが増えてしまったからだろうか。自分で自分が分からない。あんなに願ったはずの自由すら時折疎ましくなるのも、
「…」
――彼がこの本丸を去る後姿を、いつも嫌に思ってしまうのも。
ただその名前を呼んだだけで、胸がじくじくと痛んで、宗三はしかめ面になった。自分は気が違ってしまったんだろうか。行儀悪く畳の目をつめ先で猫のように引っかきながら、宗三は自問自答する。
たとえ主であろうと、彼がどこで何をしていようが、自分には関係ないはずだ。
意地になってを目で追えば追うほど、彼は己にも、ましてや何ものにも執着していないことをまざまざと思い知らされた。顕現した時に一瞬見せた、情感なく冷めた瞳。あの瞳に射抜かれた瞬間から、宗三の心だけがこの本丸に囚われたままなのかもしれない。
この本丸に、は不在なことが多い。でも、が好きだからといって一向に変えないこの春の景趣だとか、出て行ったが開けっ放しにしたままの押入れの襖だとか、そんなものがの残り香を漂わせて、いやに寂寥な場所に思わせて、宗三の心を縛ってしまうから。
見ない振りをしてきた感情が喉奥でひっかかったまま、気がつけば、見苦しい執着が宗三の中で顔を覗かせつつあった。
「…あえ、宗三ぁ…?」
とろとろとした声が聞こえてきて、気持ちが沈みつつあった宗三はどきりとしながら我に返った。がめずらしく傍にいるせいで、あれこれ長く考えすぎていたらしい。
顔を上げると、が薄暗闇に目をならすように宗三のほうを藪にらみしていた。
どきどきとせわしない心臓をいさめて、宗三はいかにも落ち着いています、なんなら少し呆れていますという顔を作って口を開いた。
「…起きましたか。無用心ですよ…開けっ放しで」
「ん、」
のそのそと起き上がったは顔を擦っている。ふあ、と猫のように大口を開けてあくびしながら、覚醒を待っているようだった。宗三といえば、先ほど触ってしまったの髪の感触や、馬鹿みたいに彼の名前を口にしてしまったのを今になって思い出して、羞恥と後悔がごちゃまぜになって爆ぜそうだった。
「よく寝たわあ」
「それはよかったですね」
「ん。…はあ、顔洗ってさっさと準備しよ」
「、」
立ち上がったに宗三はつられて立ち上がり、つい、その袖を掴んでしまった。薄暗闇の中で、振り返った寝ぼけ眼が宗三を捉え、次いで引っ張られた袖を見やる。
「…何すか」
怪訝そうなが、至極冷めた声で問いかけてくる。
その声色には、いつかの冷たい瞳の片鱗がわずかにうかがえた。自分に熱を上げない者の瞳。宗三に全面的な好意を持つわけでない、人間。――の気持ちがわからないから、不安だ。
宗三は、相手のことを推し量る努力をしてこなかった。ただ流されるままの宗三にとって、それは必要のない、無駄なことだったはずだから。
「あ…」
宗三は言葉を失くした。咄嗟に動いた手は自分に正直で、はしたなさに恥じ入るような気持ちになる。
本当は――行ってほしくなんかない。もっと一緒にいて、を知りたい。
けれどもその願いを口にしてしまえば、自分を縛ってもてあました彼らのように、この気持ちが卑しいものに成り下がる気がした。それにこの気持ちを口にすることは、自分の主張にたがう。きっとも、面倒だと思うに違いない。
いつになく長い時間2人きりでいて、その上宗三がうんともすんとも言わないので、さすがのも戸惑っているようだった。やがては息を吐いて、袖を掴む宗三の手へ己の手を重ねた。
思っていたのとは真逆に、ゆっくりと優しく指を解かれて、宗三は心臓が止まりそうだった。こんな時になんて優しい触れ方をするんだと思うといよいよ泣きそうで、離れられなくなる。
「…宗三?……俺、もう、行くね」
後ろ髪をひかれるようにそう言いながらも、が宗三に背を向けた。
が障子に手をかけて隙間をつくる。ああ、行ってしまう。
突き飛ばしてやりたくって、でも、本当は、追いたかった背中。
胸が絞られるように痛い。ずっと欲しがられるばかりで、こんなに欲しいと思ったことはないから。本当に、どうしたらいいのかわからない。宗三はもう一度、今度はの服の背中を掴んだ。先を行こうとしたが、後ろに引っ張られてよろめく。
何してるんだと真っ白な頭で考えても答えはでない。こんな子どもじみた真似をするつもりはなかった。今すぐこの腕を切り落とすか、刀の身に戻ってしまいたい、なんて無茶なことを考える。
それでも、手は離せなかった。
「……あのさあ…もしかして…………、行ってほしくないの?」
「…、…」
に核心を突かれて、握り締めた手にぎゅっと力がこもる。「…なんでしゃべんねえの」が困ったように訊ねた。
宗三は言葉を探した。ひとつ間違えれば、自分の中で何かが粉々になりそうだった。
自分の気持ちに素直になることがこんなにも不安だなんて。宗三は今、自分が世界で一番弱い生き物のような気がした。
「…縛っては、いけなかったんです」
宗三はおそるおそる口にした。声が情けなく震えたけれど、すぐ傍にいるにもはっきりと聞こえた。
宗三の、自嘲のような笑いを滲ませるいたいけな言葉を、は黙って聞いていた。
「ただあることを求められるのは、…辛いことだって、僕、知ってるんですよ…」
「知ってる、はずなんです…」薄氷を踏むように言葉を選んでは言い訳を重ねて、宗三は醜い本心をうまくごまかそうした。
今までの自分を守るために、何より――に疎ましく思われないように、上手に取り繕ったつもりだった。
「…」
けれども全くへたくそなそれに、は前を向いたまま、拍子抜けしそうになった。
細い陽の光がに向かって手を伸ばすように差し込んでくる。
障子の隙間からは、の好んだ春の青天が見えた。広い世界の下、はちっぽけな自分を確認するのが好きだった。
けれどもなぜだろう、今はそれほど、あの青空の下に飛び出していきたい気分ではなかった。
それよりも――この宗三と二度寝でもしようか、なんて。ふいにおかしなことを考えた自分に、は数秒固まって、それから、自分に呆れてこっそり笑った。
「………ん…俺、こんなだけど。…別に刀1本くらいにわがまま言われたって気にしない」
進退窮まった空気に、の、へらっとしたような、ふらふらしたような、浮ついた言葉が落ちる。
「………」
その瞬間、神妙にしていた宗三の片眉がやや上がった。…なんだその言い方。ばしん、と無神経で無粋なの背中を叩く。「いって、お前、案外力強いんだから気ィつけて」…だから、なんだ、その言い方。案外?今度はぺちんと背中をはたいた。
「うおっ、」
――それから堪らずに、握り締めた部分をこちらへ手繰り寄せて、その背中に顔を埋めた。の腹に両手を回して体ごと密着する。の背中は案外熱い。の香りに混ざって、ほんのりイグサの匂いがする。それになんとなく安心した。
「…宗三?」が名前を呼ぶ。宗三は顔を埋めたまま、返事をしなかった。
今溢れるばかりのこの気持ちを、率直な言葉へ変えることは宗三にとってまだまだ難しいことだった。
がおもむろに、腹に回された宗三の腕へ掌を滑らせた。前で硬く結ばれた掌までたどり着いて、甲をなだめるように軽く叩く。
そんなの掌の気軽さと温かさに、ぽっかりと満たされないでいた宗三の心が、簡単に、ちょっぴり埋まった気がした。
押し寄せてくる何かに耐えるように、宗三はの背中に額を押し付けて、強く目を閉じる。――こんなに自由になったせいで、今度は、貴方を縛りたくなってしまった。
「(…あなたの、せいだ)」
「……あり?、でかけんがか?」
掃き掃除中の陸奥守は、未だに軽装のを見とめて声をかけた。昼寝から目を覚ましたら、いつものように早々に出かけるものだと思っていたのだが。不思議そうにする陸奥守の足元には、桜色の花びらが絨毯のようになって円を描いていた。
「ん、…ちょっとやめた」
そういうの影に誰かいるのに気がついて、陸奥守は、おや、と箒を片手にぱちくりと目を瞬かせた。視線の先には、俯いてふてくされた顔をしているのに、の服の背中を幼子のように離さず握ってついている宗三がいた。
「なんじゃあ、かわいいのを連れちょるの…」