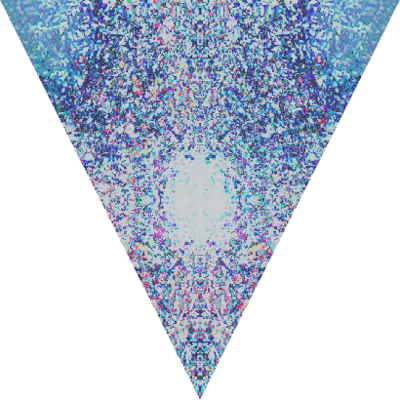
メメント・モリ
「全く、生者の考えることはわからんな…」
短くなった煙草を1本ふかしながら、スーツ姿の肋角は目の前の白亜の御殿を見上げた。図々しく佇むそれは、田舎のこの港町には不釣合いで、どこか胡散臭かった。
変なことをしでかしている人間がいる、という情報が、肋角の属する特務室に入ったのはつい数日前のことだった。
「…変なこと?」肋角が詳細を聞くと、どうも霊能力者を自称するその人間が呪術行為を頻繁に行い、出鱈目なそれが偶然にもよくないものをむやみやたらに現世に召還して集めてしまっている、という頭痛のするような案件だった。普段人間たちに危害が及ばないよう配慮をしているのというのに、なんという仕打ちだろうか。
しかたがないと現地へ赴き、肋角はその霊能力者の娘――と偶然出会った。
肋角の案内役を任されたらしいは、母親と違って本物の霊能力者だった。なんせ、スーツ姿で現世に馴染んでいたはずの肋角を、「あなた、人間じゃない」と一瞬見ただけでものの見事に言い当てたくらいだ。
のような人間は、ごくたまに見かけることも、聞くこともある。人間たちはまがいものの母親に気を取られて気づいていないようだが。
は肋角の素性を尋ねると、どこか納得した様子で、それ以上言及してこなかった。
「――ちょっと待って!」
一通り件の張本人の下見を終え、去ろうとする肋角に声をかけたのはそのだった。
慌てて駆けてくるに、肋角はその場に立ち止まると咥えていた煙草を口から離した。
「何だ?」
「私、…何か手伝おうか」
わずかに目を見開いて驚く肋角に、は静かに笑った。
「あなた一人でやるの、絶対に無理だよ。私のお母さん、人の話なんて聞かないの」
肋角は思わず黙り込んだ。確かに、試しに会ってみたところ、の母親はどこか神経質で、よくない方向に猪突猛進であり、来訪者であるはずの肋角の話など全く聞く耳持たずだった。かといって、下手に刺激して睨まれてしまうのも困る。肋角の目下の悩みはそれだった。
手伝おうなどと言われると気持ちが揺らぐ。肋角以上に、は自分の母親のことを熟知しているはずだ。
「私、協力する。絶対誰にも言わないから」
「だが、」
「約束する」
強く言い切るに、肋角はややあって、はあ、と息を吐き出した。
「…ありがとう、感謝する」
肋角が素直にそういうと、は満足げに目を細めた。
それから内緒話をするように声を潜めて、上目遣いに肋角を見上げる。透き通るようにまっすぐな瞳は、ここに来るまでに見た青空のようだった。
「協力する。だから…あのね……私と、お話して」
「この家には誰も寄り付かないから」と言うに、肋角は言葉に詰まった。
初めてを見たとき、見た目から推定される年の割りに、どこか幼く感じられた。その理由が、彼女の今の一言に詰まっているような気がした。大きな家に、彼女とその母親だけ。母親は偽の霊能力で名声と富に溺れ、聞く耳持たず。がどんな気持ちで過ごしているのか、肋角でも容易に想像がついた。
――この時の肋角は、を放っておけないと思った。面倒見のいい肋角だったが、に対するそれは、斬島たちを拾った時とは少し違うような気もした。
は報告会と称して、肋角としばしば会いたがった。
この家には誰も寄り付かないから、というのは本当なのだろう。毎晩、の部屋で報告を受けるのが定例になっていた。肋角は当初、若い娘の部屋に入るのもどうかと思っていたのだが、はどうでもいいようだったので、そのうちほだされて気にしなくなってしまった。
はいつも、肋角に簡潔に報告を済ませると、すぐにはしゃいでおしゃべりを始めた。時々「母親のせいで父親が家を出た」というような、肋角がひやりとする爆弾話もあったが、そんな話でものトーンは変わらず、まるで面白い昔話でもするかのようだった。それがまた妙に、肋角のへの庇護欲をかきたてた。
対話に慣れていないのか、前のめりに勢いづいたそれを、肋角は不快に思うことはなかった。そのうち打ち解けてくると、肋角からも仕事に差し支えない程度の話をするようになった。
今夜もは、ベッドに横になったまま夜通し話そうとする。同じ屋根の下にいる母親に聞こえないように、小さな声で。
やがて頭がうつらうつらしだして、言葉が途切れがちになる。重たく上下するの睫が、かげろうの羽のように繊細で美しいことを、肋角だけが知っていた。
突然、こてん、と糸が切れたように眠ってしまったの頬に、青白い月の光が差し込む。肋角はが眠りやすいように体勢を整えてやって、髪を梳いた。それから己の取った行動に、はあ、と溜息をつく。
――夜、が眠りだした時から。肋角の本音がこっそりと顔をのぞかせる。
の頬をそっと撫でてやると、はくすぐったそうに少し身をよじった。それが猫のようで、肋角は思わず笑った。
ベッドサイドランプのつまみをひねって灯りを消すと、部屋の中を照らすものは月明かりだけになった。肋角は、ベッドの横にある窓を開けて手持ちの煙草に火をつけた。窓の外には、砂を零したように数多もの星が散らばっている。じっと見ていると、時折流星が見えることもある。田舎の高台に立っている豪邸なだけあって、眺めは一等級だった。
肋角が獄都から持参している煙草は、匂いもするし煙も出る。灰も落ちる。けれども、それが現世に居残ることはなく、文字通り跡形もなく消える。元々相容れないものを無理やりこちらに持ってきているのだし、こちらに跡を残してはいけないのだから、当たり前といえば当たり前だ。
は肋角が煙草を吸うことを許可していた。肋角は少々遠慮して、が眠っている間だけそれを口にすると自分で決めていた。どうせ人体にも影響はない。
「…」
短くなる赤い穂先を見つめて、肋角は目を伏せる。
肋角が、眠っていると暗闇の中にいる。それが2人の本来の、正しい距離であるような気がした。
肋角は実直であったが、それでもあちらの世界の生き物だ。人間からすれば、後ろめたく感じられることだってしている。はおかしな母親に振り回されながらも、どこかで純真さを失ってはいない。この真逆の2人が、普通なら恐らく出会うこともなかっただろうに、ひょんなことから繋がりを持ってしまった。
楽しそうに話をするの顔を思い出して、肋角はつい笑みを零した。まっすぐなといると気が楽だった。とても不謹慎だが、この任務が終わらなければ、とも思う。という人間に、必要以上に入れ込みすぎていることを、肋角は重々承知していた。
それでも、のために何かしてやりたいのだ。
煙草から落ちた灰が、地面につく前にさらさらと空中に消えていく。それをどこか虚しく見つめながら、肋角は星を見上げた。
には何も残してやれない。この煙草のようにだ。肋角がどんなに残したくても、交わした言葉と、触れた感触くらいしか残ってくれない。だからせめて、自分との関わりが、彼女のためになると信じたい。自分を手伝うと申し出てくれた彼女の、笑顔の糧となることを信じて。
そうして幾度かの夜を迎え、肋角の仕事が、ようやく終わりに近づいた。
がうまく立ち回ってくれたお陰で、あの母親がよからぬものを召還することはなくなった。相変わらず出鱈目な呪術を行ってはいるようだが、こちらとあちらが繋がらないのなら何の問題もない。
昼食終わりのに無事仕事が終わりそうだと告げると、嬉しそうなにせっかくだから少し話そうと散歩に誘われた。
こうして2人でのんびり出歩くのも、もう最後なのだろう。のどかな港町にかもめの声がする。縁石の上に乗り上げて、は器用に肋角と進んだ。の切りそろえられた毛先は海風に揺られ、太陽の光で金色に光る。肋角は目を細めた。の淡い黄色のワンピースの裾がぱたぱたとはためき、目を離したらふわふわと宙に歩いていきそうだった。
肋角は、こうしてと散歩をするのがすきだった。がどんなに仕立てのよい服を着て、立派な家の中で高級な家具たちに囲まれていても、彼女が一番輝くのは青空の下だという確信があった。肋角が夕闇からの世界に生きるのなら、は朝焼けからの世界に生きるのだろう。
2人で過ごすうち、には心からの笑顔が増えたように思う。それを密かな幸せとして毎晩ふかす煙草は、いつもよりうまいような気がした。
「肋角さん、この仕事が終わったらどうするの」
「もちろん、帰る。獄都は万年人手不足だからな」
「ふうん…」
「君は?」
「……どうしよっかなー、私」
何気ない会話の中で、が少しだけ顔を曇らせた。
聡明さを潜ませるその瞳を翳らせるのは、きっとあの母親だけなのだろう。
「…私、肋角さんに会ったから」肋角に聞こえるか聞こえないかの大きさで、はふいにぽつりと呟いた。水平線の方へ視線を向けるの横顔は、大人びた秀麗さがあった。
が肋角を振り返り、あいまいに笑った。
「きっと私、今まで、死んでるか生きてるか、わかんなかったの。だから、どうしたらなんて考えたこともなくて…」
「…」
「でも、やっとわかった。…私、生きてたんだね」
の瞳は、じっと肋角の瞳を見つめている。
焼き付けるような苦味の上を、優しく清涼な風が吹き抜けていく。たとえ住む世界が違うことに胸が痛んでも、と出会えたことを、肋角は後悔しなかった。それはも同じだと、そう思いたい。
「私も、私の人生、生きてみよっかな」
「…ああ」
肋角が口角を上げて手を差しだすと、 はそっと肋角の掌に自分の掌を重ねた。大きな掌に包み込まれるのそれは、安心しきって全てを委ねている。
手に入れたいと、思うこともある。――でもそれ以上に、彼女が自由にしている姿を見ていたい。きっとそれが、の一番輝ける、美しいあり方だ。
数奇な人生を歩みながら作り上げられてきたはずのの笑顔は、いつしか自然でまばゆいものへと変わっている。肋角が手を伸ばすのも、少し躊躇われるほどに。
繋いだ手にが力をこめる。肋角も力を少しだけ入れかえして、再び歩き出した。
2人の間に言葉はなかった。けれども、強い何かが、お互いを繋いでいることを知っていた。
最後の夜。めずらしく駄々をこねるに根負けして、肋角はのベッドに入って一緒に寝てやった。
「今日は絶対起きてる」と勇んでいたのに、いざとなるといつものように眠ってしまったに笑いながら、肋角はその髪を何度も梳いた。ただ安らかに眠るその姿を、しっかり目に焼き付けた。
徐々に夜の帳が上がり、朝が姿を見せ始める。
夜と朝、2つが交わるほんの一瞬。夜は朝を飲み込んではいけない。その朝が来る希望を、――の未来を、大切にしよう。
やがて朝陽が目に染みて、肋角は目を細めた。彼女の時間だ。
肋角はいつも、朝を迎える前にの家から去っていた。だからこそ、こうして一晩過ごせたのは感慨深い。おはよう、とたった一言と交し合えたことが、たまらなく幸せな気がした。
寝落ちてしまったことにしょんぼりしているを慰めてやって、母親が起きてくる前にと肋角は手を繋いで家を出た。
しばらく港沿いを歩いて、ここまででいい、と肋角は繋いでいたの手を解いた。道中、言葉少なだったがはっとしたように顔を上げた。
「…、もう終わり、かあ」
「、」
「ふふ、うちのお母さんなかなか曲者だったでしょ?おつかれさま」
「…」
肋角に一言も漏らさせまいとするように、は平気なふりをして空虚な言葉を連ねる。痛ましいそれを、肋角は黙ってみていた。
それでも次第に言葉に詰まって、は笑顔のまま顔をくしゃりとゆがませた。
「…いやだなあ。バイバイしたくないな」
鼻にかかったような声で、は無理に笑おうとする。肋角はその体を引き寄せた。
小さな頭を抱きしめて、あやすように何度も髪をすく。毎晩優しい気持ちで触れていたそれは、よく手に馴染んでいる。
の手は、震えながらやんわりと肋角の服の胸元を掴んでいた。
その健気さを見れば、肋角の口からは、の幸せを願う言葉が自然と零れ落ちた。
「…精一杯生きて、人を愛して、…幸せになりなさい」
「………、肋角さんが、そう言うなら」
声を気丈に奮い立たせて、はそうか弱く呟いた。
肋角はの丸い頬を両の掌で包んで、上を向かせる。はとうとう我慢できなくなったのか、子どものように酷くしゃくりあげていた。大粒の涙が頬の上を零れ落ちて、肋角の手を濡らす。肋角には、それすら愛おしかった。
聞いているほうの胸が張り裂けそうな声で、は言葉を必死に紡いだ。
「私、幸せになるから。後悔しないくらい、頑張るから、」
「ああ」
「だから、………死んだら、会ってくれる?」
その幼い泣き顔に似つかわしくない物騒な言葉に、肋角は思わず笑ってしまった。
それから――胸に湧き溢れる愛おしい気持ちに、そっと鍵をかけた。
の薄羽のような睫を、涙がしとどに濡らしている。約束だってなんだって、してやろう。だから、もう泣かないでほしい。
「――待っている。いつまでも、ずっと」
この世界のどこにいても、きっと見守っている。いつかが自分のことを忘れて、約束をたがえてしまったとしても。それでも、ずっと。
この体ある限り、心をに捧ごう。
の体を腕の中に抱きこんで、肋角は細い肩を、その体の小ささを記憶する。の髪からは、石鹸の香りに混じって、海風の匂いがした。
「肋角さん、」
さよならを喉奥に押し込んで、肋角は唇をそっとの額へ触れさせた。
反射的に目を瞑ったは、その優しさに、泣き顔のまま自然と笑みを零した。
――次にが目を開けたとき、肋角は消え、ただ、潮騒だけが遠鳴りに聞こえた。
2人を分かつのが生だとしても、愛おしい気持ちはここに置いていこう。いつか君と、また通い合う日まで。