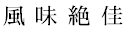
幼い頃から、他の人には見えないものが見えた。
両親も親戚も普通の人。私ももちろん、普通の子どもだった。
なのに、お化け――いわゆる人でないもの――に、異様に好かれる子どもだった。
“危ないな”
黄昏時、泣きながら逃げ惑う私の手を引いた大きな掌。
鼻をくすぐるタバコの匂いは、臭くて大嫌いなはずなのに、小さな私はとても安心してまた泣き出した。
私を助けてくれたのは、優しい鬼だった。
👻
アー、アー、と遠くから烏が鳴く声がする。
朱色に滲む逢魔時。
優しい鬼いわく、「私が狙われやすい時間帯」。私にとっては、彼によく会う時間。
「…。何をしてるんだ」
「…ハロウィンです」
「こんな時間帯に1人でうろつくな」
学校の制服に悪魔の角を模した赤いカチューシャをつけて、何をするでもなく鞦韆に揺られていると、どこからか音もなく鬼こと肋角さんが現れた。
出会った時と全く変わらないその容姿は、人によく似ていても、やっぱりどこか違う。
いつもの煙管ではなく、紙巻煙草をふかして仁王立ちしたままの彼に、私は首をかしげた。
肋角さんはそんな私に呆れたように、ふう、と紫煙を吐き出す。
「今日は仏滅で、新月だから月明かりもない」
「?」
「…要するにあまり、よくない」
歯切れの悪いその言葉に、私の前に唐突に現れた意味を理解する。
てっきりハロウィンだから遊びに来たのかな、なんて期待したのは間違いだったようだ。
「でも、友達と、遊ぶ約束してるし…」
「…」
肋角さんの、帰りなさいと暗に促す視線が痛い。
わかっている。何も彼は、意地悪で私に帰れと言っているわけではないし、むしろ心配してくれているんだろう。
煮え切らない気持ちのまま、けれどもこのまま我儘を言うのも憚られた。言い訳をもごもごと口の中で転がしながら私はうなだれた。
「…肋角さんが言うなら、帰ります」
決して自分の意思ではないことを明白にしたのは、ささやかな反抗だ。私はいたって普通の人間なのに、なんで普通に暮らせないんだろう。
友達に合流できない旨のメッセージを送ると、いよいよ気分が落ち込んだ。浮かれたカチューシャも取ろうとすると、おもむろに肋角さんが目の前に膝をつき、私の方へ手を伸ばした。
「わ、」
わしわしと大きな手の平に頭を撫でられる。髪がぐちゃぐちゃになったし、カチューシャがすこしずれた。
帽子の鍔の下から覗くのは異様な赤色の目。
ただ、それが深く優しい色をしているのを私は知っている。小さい頃から、彼はこうして視線を合わせてくれるから。
「」
赤い瞳を探るようにじっと見ていると、肋角さんが大きな掌を差し出す。
王子様みたい、と思ってしまったけれど、こんな人相の悪い王子様はきっといないだろう。
「…仕方ない。しっかり手を繋いでいろ」
👻
「肋角さん!」
私たちの背後から響いた声に振り向くと、紫色の目をした肋角さんのような格好の人――たぶん獄卒だろう――がいた。
彼は肋角さんの腕にしがみついた私を見つけると、鋭い眼光でぎらりとこちらを睨んだ。肋角さんといい、鬼は恐い人しかなれないのだろうか。
「(ひえ)」
「…そちらは?」
「谷裂、ご苦労。…旧い知り合いだ。案内中だから、後はよろしく頼んだぞ」
肋角さんに手を引かれ、私たちは再び歩き出す。
獄卒の彼は気合の入った返事をすると、再び列の誘導に戻ってしまった。後ろから、「こちら江戸区域、」無線に向かって話す声が聞こえてくる。
彼が整列させているのは、人間ではない。
妖怪たちの行列。いわゆる、百鬼夜行だ。
肋角さんに連れられ、私は獄都へとやってきていた。普段話に聞いている獄都に来るのは、これが初めてだった。
私と肋角さんは妖怪達の川を横切り、しばらく歩いて、小高い丘へと上がった。
「わ、」
見晴らしのいいそこから見下ろすと、私たちがいた場所は様々な妖怪でごった返していた。
まさかあそこまで混んでいたとは思わず、思わず呆けてしまう。
「…代わりにはならんだろうが、これで我慢しなさい」
肋角さんの言葉に、ぷ、と私は噴出した。
「私別に、お化けが見たいわけじゃないんですよぅ」
肋角さんが考えに考えたハロウィンらしいことがこれだったのだろう。
でも、私みたいな女の子が考える10月31日には程遠いと思う。物珍しさはあるかもしれないけれど。
「…」
「ふふ」
決まり悪そうに黙り込んだ肋角さんに、私は思わず笑った。
それから、ふと、先ほど歩きながら考えていたことを口に出す。
「…私、なんで大丈夫なんですか?」
あんなにも近くを通ったというのに、妖怪は1匹も寄ってこなかった。
それどころか、まるで私まで人間じゃないように自然にあの中へ溶け込んでしまっていた。
「今、お前の気配を消している。よもや生者とは思われないだろう」
ぐ、と握られた手に力が籠る。一瞬たりとも手を離さなかったのはそういうことらしい。
手を握ることに何の意味もないと分かったはずなのに、つい顔がかっと赤くなる。思わず俯いた。
「…いいんですか?こんなところに連れてきて」
「どうせ今日は、日暮れからお前を見ているつもりだった」
「…そーですか」
一緒にいるのがデートでもなく、監視目的というのは、喜べばいいのか落ち込めばいいのか。
…まあ、いいか。今は、2人でいられる時間を味わおう。そう思って、私もゆるく手を握り返す。
さらりとした風が髪を攫い、私は顔を上げた。遠くから囃子の音がわずかに聞こえる。
どこか懐かしいような、それでいて妖しく誘われているような不思議な音。
「…きれい」
ぽつ、ぽつ、と淡い橙の光が遠くに点滅しているのが見える。通るときにもいくつか見た提灯だろうか。今夜は月も隠れているから、その光は一層力強い。
ぐねぐねした異形たちの群れは、まるで1匹の大蛇のようだ。彼らは夜通し歩いてどこへ向かっていくのだろう。
百鬼夜行を夢中になって目で追う私に、肋角さんはただ、黙って傍にいてくれた。
👻
肋角さんと手を繋いだまま、私は帰路についていた。
宵闇の中でも、肋角さんがいるだけでとても心強い感じがする。
友達との楽しいハロウィンパーティーには程遠いけれど、肋角さんが私のことを考えて動いてくれただけで、今日はとても嬉しかった。
それに、肋角さんが普段住んでいる獄都の空気も吸うことができた。一生の思い出になりそうだ。
「…あの、肋角さん」
「なんだ」
「ありがとうございます。一番面白いハロウィンだったかも」
素直にそうお礼を言うと、肋角さんはちらりとこちらを見て微笑んだ。
その優しい顔にどきりとして、私はもぞもぞと口をつぐむ。
が、ハロウィンらしいことをもう1つするのを忘れていて、私はぱっと顔を上げた。
「あ」
「せわしないな。どうした?」
「トリックオアトリート!」
「?」
私が繋がれていないほうの手を差しだすと、耳慣れない響きに肋角さんが首をかしげた。しかしすぐに思い当たることがあったのか、「ああ、」と納得したように呟いたきり、眉を顰めて黙り込んでしまった。
…うん、まあ、もらえないだろうな。言うだけタダだと思って言っただけだし。
冗談です、と続けようとした瞬間、「これぐらいしかないな」と肋角さんが何かを取り出した。
「えっ」
「…どうした?これでいいだろう」
私が驚いたのは、なにも肋角さんがお菓子を持っていたからではない。
ずうっと前、小さい頃にも、似たように肋角さんに食べ物をせがんで、突っぱねられたことがある。
それは“黄泉戸契”だから、と。
あちらの世界で作られた食べ物を食べたが最後、人間は現世にとどまっていられなくなる。あちらの世界のものを食べたことで、人間ではなくなるから。
だからそういうことは、自分の立場からはできないのだと。
私は信じられない気持ちで、おそるおそる掌を差しだした。ぽとん、と呆気なくそれが手の中に落とされる。
小さな立方体のそれは、どうやらキャラメルのようだった。
「あ、ありがとうございます…?」
もうずっと前から、肋角さんの傍にいたいと思っていた。
でも肋角さんは責任ある大人で、私がそちら側へ足を踏み入れることを許してはくれない。私も肋角さんに厭きられたくなくて、聞き分けのいいふりをしていた。
だのにまさか、それを許すような行為を肋角さんがするとは。
包装紙を開くと、普段食べているものよりも数段甘い香りが漂っているような気がした。
その甘い香りと、興奮と、そして少しの緊張で、頭がくらくらする。
「、あっ!?」
――しかし、意を決して口の中にそれを放り込もうとした瞬間、肋角さんがそれをひったくって自分の口に突っ込んでしまった。
「、甘い…」
「…、…」
もご、と口の中でキャラメルを転がしながら、肋角さんはそう呟く。私は呆然と、肋角さんの口の中へ消えていったキャラメルを見ていた。
私の手元に残ったのは薄い包み紙だけ。渇いた口には甘ったるかったのか、肋角さんは眉をしかめてキャラメルをぐにぐにと噛んでいた。
キャラメルをすっかり小さな破片にして飲み込んでしまった肋角さんは、帽子の鍔を下げて私をちらりと横目に見た。
「冗談だ。ちょっとした悪戯だろう」
「…」
不服そうに包装紙を畳んでポケットにしまう私を見て、肋角さんは口はしを吊り上げて笑った。
笑えない冗談。いっつもそうだ。私が肋角さんを振り回しているつもりでも、最後は、何故か肋角さんに惑わされている。
「…いつか、食べてやる」
私はふてぶてしくそう呟いて、つながれたままの手に寄りかかった。
肋角さんはそれを振り払おうとはしなかった。帰り道は、あとわずか。
「(いつも、そうやって)」
自分も鬼だと忠告はするのに、拒絶まではしてくれない。私の気持ちなんて、絶対、見透かしているくせに。
だから私はあきらめきれない。肋角さんへの思いも、そちら側へ行くことも。もう普通になりたいなんて贅沢はいわないから、せめて、肋角さんの特別になりたい。
――私の未練がましい初恋の責任を、早く取ってくださいよ、肋角さん。
私の気持ちを読み取ったのかそうでないのか、肋角さんが揶揄するように口元に弧を描く。
「こちら側に来るには、早い、早い」
キャラメルの甘い香りに混じって、煙草の、たまらなく苦い香りがふわりとした。