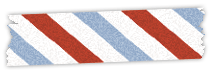
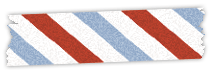
「昨日の帰り道ね、黄色い風船が飛んでいくのを見たんだ」
「ふうん」
「誰かが離しちゃったんだろうなー、とか持ち主可哀想だなー、とか思ってたんだけど」
「うん」
「でも空の青さとその黄色が妙に合っててね。なんか可愛いなーって思った」
そう言いながら、彼女は両手を小さく擦り合わせた。
僕の彼女はおしゃべりが大好きだ。
だけど、喋りが上手いので退屈しない。むしろ面白い。
笑顔がベースの表情も、話の切り出しも。
彼女にかかれば、昨日の夕飯の様子でさえ、面白い話に早変わりする。
僕はといえば、あまり喋るのは好きじゃない。
だからいつも受身だ。返事も月並みだし、気の利いた話題も振れない。
ふと気になることがあったので、彼女に尋ねてみた。
「君は僕といて、退屈じゃないの」
尋ねた後に、この質問は無いかな、と少しだけ思った。
彼女は驚きを顔にまぶして、質問を質問で返す。
「……雲雀くんは、私といて退屈なの?」
「全然退屈じゃない」
思わずそう言うと、彼女は嬉しそうに笑った。
白い息が、口端から漏れる。
「私も雲雀くんと一緒。いつも私ばっかり喋っちゃうけど……雲雀くんが、おもしろそうにしてくれてるから、いいのかなって」
「おもしろそうとか、わかるの」
「うん。顔が笑ってるよ」
彼女自身も微笑みながら、そう指摘する。
少し驚いた。
僕はあまり、表情に出さないタイプだと思っていたんだけど。
そんな僕の考えを見透かしたように、彼女は笑った。
「雲雀くんは、接してみると案外素直だよ」
「……君は、本当に素直だけどね」
「よく言われます」
裏表が無くて、いつも楽しそう。彼女の印象は、大体そんな感じだ。
僕としては、その笑顔の源はどこから来ているのか不思議だ。以前に尋ねた事があったけど、
「さぁ?チョコがおいしいからかも」とお菓子を食べながらいい加減に答えられてしまった。
顔の作りもいいし、性格もいい。僕としては、そういう人間にであったのは、初めてだった。
初め会ったときは、こんな奴が本当にいるのかと感心してしまったくらいだ。
先ほど案外素直だと言われたけど、もしかしたらそれは彼女に出会った影響かもしれない。
彼女の不思議な魅力を、また一つ知った気がした。
僕のつまらない質問が、たわいない会話へと変わる。
それぞれの話題が軽くスカスカに感じられないのは、彼女の嬉しさや喜びが詰まっているからだと思う。
だから、彼女とのおしゃべりは楽しい。
「そういえば、昨日私の夕飯、お鍋だったんだけど、雲雀くんは何食べた?」
「……カレーを食べたよ」
「カレーかあ。カレーいいよね。簡単に作れるし、おいしいし。ずっと前、カレー作りにハマって何回も食べたよ。
そういえば、近所のおじさんがよくじゃがいもとかくれるし、今日はそれでカレーにしてみよっかな」
彼女の話は続く。飛びつづける風船みたいに、ゆるやかに。
僕はそれに掴まる。それだけで、簡単な幸福の出来上がり。
ふと気付いた。
僕は彼女といると、素直になれるだけじゃなくて、幸せになれるみたいだ。
自分でそう考えて、少し照れた。
照れ隠しに、彼女の手をちょっとだけ掴んでみる。
彼女は少し驚いて、照れながら、軽く指を絡めてきた。人さし指と中指が、手の中の籠におさまる。
指先は、つららみたいにつめたくて、ひんやりしていた。
彼女は話を続ける。家について、僕らがさよならするまで。