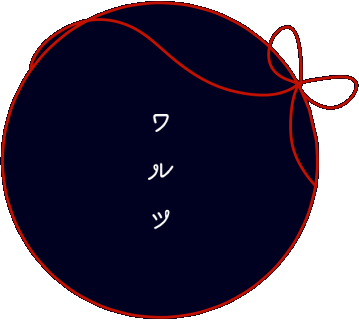
「もうすぐ盆だなあ」
もごもごと口の中を西瓜の果汁でいっぱいにしながら、審神者はしみじみと呟いた。
それは年幼い審神者が就任してまだ間もない頃の夏。皆が寝静まった縁側でのことだった。
岩融の主は見た目や年の割りにしっかりしていて、例えるなら物静かな薬研のような少年だった。昼間甚平姿に扇子で顔を煽っていたところなど、どこか食えぬ大物のような貫禄を持っていた。
近頃はにょきにょきと背が伸び、声変わりも始まったが、まだまだにごりきらないその声が夏の夜庭に涼やかに響く。
あんぐりと口を開けて西瓜をかじろうとしていた近侍の岩融は、審神者の言葉を聞いてああそうだな、と思う。
ただ、岩融は人でもないのでそれ以上どう話題を広げていいものかわからず、ひとまず口の前で食べられたそうにしている果実へかぶりついた。しゃく、という音と共に手に冷たい果汁が滴って、岩融はぴっぴと手を払った。井戸に入れっぱなしにしていたのを先方取り出したからよく冷えている。審神者が西瓜の種を器用に吐き飛ばした。光忠がこう切れば種が邪魔にならずに食べやすいといっていたのに、勝手に切って夜中に2人でこっそり食べているので、たぶん明日には彼から大目玉を食らうに違いない。早いうちに長谷部を味方につけておかねばならないだろう。
岩融が黙々と実を食べつくしていると、審神者が後ろ手をついてほうとため息をついた。
「やっぱりしないな」
「?」嚥下しながら岩融が首をかしげる。視線がぶつかると審神者が目を細めた。
「こう、音がするんだな。ばあちゃん…祖母の家の近く。飛行場があってさ、なんていうか…きーん?ごおお?まあとにかく、飛行機の音がするんだぜ」
でも今蝉すら飛んでないな、と審神者は宙をやぶにらみする。岩融は「どうもうちの家系は代々目が悪いらしいな」と審神者が言っていたのを思い出した。深夜なこともあるが、彼は本当に目が悪いので何も見えていないのだろう。岩融も夜目が効くほうではないので、弱い月明かりがあってもあまり見えない。わかるのは傍にいる審神者の表情と、飛んでいく蛍の点滅光だけだ。
審神者がいくらしっかりしているとは言っても、ふとした時見せる郷愁的なまなざしが、少年の抱える物寂しさを感じさせて岩融にはいじらしい。
「そもそもひこうきがわからんわ」
「あ、そっか。今度写真見せる」
「おお、頼んだ」
「…盆になると、親戚全員で祖母の家に集まってさ。終戦記念日もあるから、飛行機の音がすると、なんだか不思議な気持ちになるんだな」
審神者の言葉の切れ端には、彼の故郷の思い出が顔を覗かせることがある。
それを愛おしいと思うのは、大切な主を育んだ土地の話だからであろうか。決して行くことはできないだろうその場所が、岩融にとっては桃源郷のような、曖昧で美しいかたちのままとどまっている。西瓜を切りながら、「西瓜ってカブトムシの匂いするよな、懐かしい」と言い出した時はさすがに困惑したけれど。
「…これ、ずっと疑問だったんだけど、今聞いていい?」
「なんだ」
「人ってさ、死んだらどうなるわけ」
岩融は首を左右に傾けて考えていたが、やがて「しらん」とだけ答えた。審神者は顔をしかめる。
「…神様なのにわからないのか?」
「所詮刀の神、全ては知らん。折れればそれで終いよ」
「そういうものか。…恐くないか?自分の意識が消えるのはさ」
若い時分にありがちな生死についてあれこれ考える行為は、この大人びた少年であっても変わらぬらしい。
岩融は快活に笑った。
「それもまたさだめかな。…だが、に2度と会えなくなるというのは、恐いかもしれんなあ」
「…何言ってんだ恥ずかしい」
じゃあ折れないようにね、と審神者がいうと、承知した、と岩融がいう。顔を見合わせて、2人は噴き出した。
「はどう思う」
「俺え?…俺は、信じてないっていうか、なんつうの」腕を組んで審神者がううん、と唸る。
「…その人を作るのは、名前とか、生まれてきた環境とか、してきたこととか…まあ、人生だと思ってるから。同じ魂でも、名前1つでも違えば違う人間な気がするよ。そもそも俺は魂見たことないし。前世の記憶があるとかいう人もさあ、それ本人にしかわかんないよな」
そういうはもう何度も人生を繰り返したかのような落ち着きぶりなのがまたおかしい。
手に止まりかけた蛍をやさしく払いのけながら、ふと岩融が「魂は見えるな」と呟いた。審神者が目を見開いて岩融を凝視する。
「…嘘、そうなの?」
「ああ、うっすらと」
「どんなん?俺のも見える?」岩融がにかりと笑った。
「蛍のような色みをしているぞ」
「…死にかけの光ってこと?」
「はっはっは、そう卑屈になるな、」
暗い中でも美しい色だ、大切にせよと岩融は瞼を伏せる。
それは事実だった。魂の色はどれほど似通っていてもひとつひとつ見目が違うが、審神者のそれは、岩融の目にはいっとう美しく光って見えた。
「子種は残したほうがいいぞ」
「…岩融、そういうの、セクハラっていうんだぜ」
「せくはら?」
「そういうこと言われるの好きじゃない人もいますよってこと。皆人生は自由に選んで好きに生きましょうねってこと」
「ああ、それはすまなんだなあ」
もし審神者が、この先何かしらの手段で伴侶なりなんなりを選び、後継を残した時。岩融は審神者の選んだ相手や子供を愛す自信があった。もちろん1番は審神者であったが。
でも当の本人がそれを望んでいないなら、未来永劫、この気持ちは彼にだけ心血注げるなと岩融は思った。季節の移り変わり、彼の隣、木々の狭間へ隠す審神者への思い。彼が健やかであれば、これ以上はいらないと刀の岩融は思う。それでも、眩い光を時たま己の手の中に掠め捉えた時、仄かに芽生えるのは笑ってしまうほど子供っぽい覚えたてのような愛欲なのだ。
「本丸が俺の行き止まりか…」
「よ、生家には戻らないのか」
「ん、まあ…そのつもりで来ちゃったし、今のとこはね。でもここにいたら、たぶん死ぬまで一人ではないだろ」
「そうだな」
「贅沢だな」
「違いない」岩融と審神者はもう一度顔を見合わせて笑った。
「…さて、どうする。もし生まれ変わったら」
「んー…。俺人間に生まれ変わる自信ないぜ」
「そんなことはないさ。それに万一姿が違ってもわかる。俺は魂の色が見えるからな」
「…俺はあいにく見えないからさ。もし、もしね。来世で会いましょうってなった時は、岩融、今と同じかっこでいてな?頼むわ」
「がはは、承知した。必ず見つけ出して見せよう」
「ちなみに岩融の魂ってどんなん?」
「ん?俺か?…西瓜の色をしているよ」
「嘘つけ」
「ん、まあ、…嘘だ」
「やっぱりかい」
「今年も無事夏が来たな」
審神者が茄子で作った精霊馬を指先でつつく。今日の夕飯は光忠の作った茄子の味噌炒めだった。
盆の時期、宵闇時。庭先には刀たちが好き勝手に飛ばし捨てた西瓜の種から芽が生えているのが見える。
岩融と審神者にとってもう何度目の夏だろう。来たころは子猫のように小さかった審神者は、今は長谷部と同じくらいの背丈だ。それでももちろん、規格外の岩融の高さには程遠いのだが。
「蛙鳴いてるなあ…なんか懐かしいわ」
「ほお?」
「じいちゃんちも辺りいっぺん田んぼしかなくて真っ暗でさ。ああでも、自然が溢れてることだけが取り得みたいな田舎だったから…川寄りに蛍がたくさん飛んでて、そこはここと違うかも」
「…そうかそうか」
「蛍いる?……いないか、あんなに綺麗なのにな」
目を凝らして宙を睨む審神者は蛍を探しているのだろうか。
ふと、岩融が審神者の眼前に己の手のひらをかざす。とがった爪がとつぜん現れて、審神者はおわ、といいながら後ろ手をついて身を引いた。それからいぶかしげな目つきで薄笑いを浮かべて岩融を見る。
「なに?」
「いいや、見えているかと思って」
「そんなに近いとぼやけるって!…でもやっぱ最近目悪くなったな、なんでだろ」
「血といっていただろう」
「え?血?…ああ、遺伝てこと?…それはないって、うち両親どっちもどっかの民族みたいな目のよさなんだぜ。うちのばあちゃんもまだ視力あるほうで」
これが隔世遺伝かと言う審神者に、岩融は「ああ、そうだったか」と郷愁を滲ませて仄かな笑みを浮かべる。それに審神者が気づくことはなかった。
ぐび、と発泡酒をあおりながら、審神者はふいにじっと岩融を見つめた。
「盆かあ……。岩融って、輪廻とか信じる?」
「ん?」
「転生とか生まれ変わりね」
「なぜ俺に聞く」
「僧侶のかっこしてるから、なんとなく。やっぱ信じる?」
あーでも、仏教っていろいろ派があるんだよね、俺よく知らないけど、と審神者が言う。
いくつになっても無邪気なその横顔を見て、岩融は裹頭を深くかぶりこみながら、そっと笑った。
「あるさ」
「? やけに言い切るね。やっぱ神様だからそういうのわかるの?」
「まあなあ…おっ。蛍がいるぞ」
「え?なんの話?ていうか嘘、どこ?」
「ああ、違った違った。見間違えた」
「………えっこわ…人魂とか…?盆だもんな…」