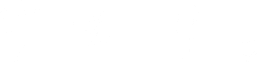──いいんでしょうか、私なんかで…。
何も着ないで寝落ちたはずなのに、目覚めると服を着せられていた。サイズの合っていないTシャツはだぼだぼで、そのせいで肌が冷えて、を中途覚醒に導いたらしかった。
ほんのりとした冷気に覆われながら、 はぼんやり瞬きする。なんにも覚えていないけれど、悲しい夢を見ていた気がする…。
明かりを落として真っ暗な部屋の中、 がベッドから体を起こして外を見やると、憂人がベランダに置いた椅子に腰掛け、たばこを吸っている。火種がゆらゆらと頼りないシルエットをかたどっても、憂人の表情は見えない。
あ、これ嫌だな。 はふとそう思う。
は、憂人が裏返ったところを見たことがない。厳密に言うと、幻影ライブでそうなっている状態を除いては、見たことがない。そのわずかな例外の時に言葉をかわしたこともないし、裏返っている憂人に認識されたと感じたこともない。
犬飼憂人という人間を作る、もうひとつの人格。恋人であってもそこに触れられない、確かめられない、という事実が、は少し不安になることもある。けれど、がそれ以上に恐れているのは、私が知りたいのだからと、優しい恋人に、自分がいつかわがままを言ってしまうこと。
相手のすべてを知ることが、知ろうとすることが、なにも愛なわけじゃないと、は身に染みてわかっている。そういう、間違ってしまった愛に支配されて傷つけられて、最後には殺されかけたを、助けてくれたのが憂人だったのだから。
家を、引き払うことにしました。
二ヶ月前のことだった。純喫茶での憂人の打ち明けに、は思わず、えっ、と大きな声を出してしまった。
その頃憂人は賃貸アパートに住んでおり、恋人であるも度々、憂人の家に招かれていた。が詳しく聞けば、職務上の都合で職場へ住み込みすることになり、自分の家を持っていても帰ることはほとんどないから、もういっそ退去することにしたそうだ。社員寮とかそういう類ではない。文字通り、職場に住み込みなのである。
からすれば信じられないことだった。仕事を終え、家に帰ることでオンオフのスイッチが切り替わる。なのに職場と家が一体化してしまったら、その辺はどうすればいいのだろう?
そんなの懸念をよそに、当の憂人はそれほど深刻そうには見えなかった。家具などを捨てるつもりなんですが、何かほしいものがあったら言ってくださいね。そんなことを言っていた。
は思わず聞いた。
憂人さ、もう家借りないなら、うち来る?
その職場環境がいかほどのものかはわからないのだが、荷物なんかがあればうちに置いていけばいい。もともとお互いの家を行ったり来たりして、寝泊りもよくしていたのだから、その延長だ。同居とは少し違うだろう。の家は単身者向けのワンルームアパートであり、個人的なスペースが別にあるというわけでもない。しかし、荷物置き場くらいにはなる。
の言葉に、憂人は童顔をより一層幼く見せる、きょとんとした表情をしていた。しかしそのあとの憂人の様子を、は鮮明に覚えている。
どう見ても、戸惑っていたのだ。
は、さーっと顔が青ざめていくのが、自分でもわかった。
やばい。いきなりすぎて重かったかな。
動揺を落ち着けようと、は、わずかにアイスが残ったクリームソーダのストローを、指でくるくる回した。メロンソーダとアイスが混じって、淡い緑になる。それはそれでかわいらしい色のはずなのに、その時のには濁って見えて、余計に焦りが募った。
自分の愛が、重いのか軽いのか。過去の経験で感覚が麻痺してしまったように思えて、はいつも、自分の行動に自信がない。
いいんでしょうか、私なんかが……。
憂人の返事は、が告白したときと似ていた。
数日後、の家にやってきた憂人の私物は、それこそいつでも旅立ってしまえるような、キャリーケースに収まってしまうほど、身軽で少ないものであった。
パンツは履いていたが、ブラジャーはほっぽり出されたままだった。締め付けが嫌だから別にいいかと、はベッドから立ち上がり、憂人のいるベランダの戸を開ける。
「」
咄嗟に灰皿へたばこを押し付けた憂人の手に、はそっと手を重ねた。
「なんで消しちゃうの?」
たばこは、の想像よりも、まだ全然長かった。
「その…匂いもつきますし、健康にも悪いので」
「それは憂人もおんなじじゃん」
困り笑いでごまかしている顔が、暗くてよく見えなかった。なんだか胸がきゅーっと切なくなって、は両手を持ち上げると、心持ち広げてみる。
「ねえ、ぎゅってしていい?」
眠るまで触れていた筋肉も、眠りながら感じていた温かい体温も。もう一回、思い切り感じてみたい。
の問いに答えるより先に、憂人がを抱きしめた。
「駄目ですよう、こんな薄着で外に出たら」
触れるか触れないか、そんな優しい手つきで、憂人がの背中をひと摩りして耳元で囁く。
けれども、宙を浮いて行き場をなくしてしまった両手に、はやんわりと拒まれた気分になった。
離して、とも言えない。でも気持ちは、正直それに近い。何を言うべき?恋人であっても踏み越えてはならない境界線を、は踏み越えたくない。ただ、何が行き過ぎた行いに値するのか、よくわからない。そうしてあれこれひとりで悩んでいるうち、息が詰まりそうになりながら、結局黙っている。そういう時に限って、の耳元で、悪魔が囁くのだ。
憂人が私の前で裏返らないのは、私に知られてまずいことでもあるんじゃない?そう、例えば、憂人が私のことを好きじゃない、とか。
「さ、中に入りましょう」
嫌な想像なんてしたって時間の無駄だ。心だってボロボロになる。わかっていても、止まらなかった。
翌朝。は、いつものように憂人を見送った。ひと眠りでもしようと思ったのに、妙に気持ちがくしゃくしゃして、うまく眠れなかった。
邪魔くさい髪をかきむしり、不意に思い立って、は憂人の置き荷物を、いくつか床に広げてみた。触ってもいいと言われているから、別に怒られはしないだろう。
水色のパーカーを両手で広げて、昨晩そうしたかったように、胸にぎゅっと抱きしめてみる。
すかすかだった。床に置かれた少ない荷物が、まるで全部、偽物のように見えた。
「24番、ください」
気づけば、は近所のコンビニまで走っていって、なんにも商品を持たず、レジの前に立っていた。
たばこの煙は、周りの人の健康に悪影響を及ぼします。
そんな文言を、消灯後の憂人は、心ここにあらずの指でなぞる。あの夜、の背中を撫でた感触を思い出していた。
の肌に、直に触れたことは何度もあった。けれど、くたびれた木綿越しに触れた、低体温の背中のほうが、本物のの肌のように思える。柔らかいけれど、脆くて、朦朧とした掴めなさが。
(やっぱり……の家を出ましょうか)
はあ、と深い溜息をつく。ここ最近、ずっと考えていたことだ。ただ、切り出し方がわからなくて、なかなか連絡はできずにいる。
決して、のことを嫌いになったわけではない。今だって大切にしたいと思っている。
たばこを吸う気分にもなれなくて、憂人はしばし目を閉じて、記憶の中にある甘い匂いを辿ってみる。
ベランダから部屋の中を振り返ると、がキッチンでホットケーキを焼いている。目が合うと、は照れくさそうに笑う。朝のニュースでパンケーキ特集してたからね、作りたくなった。そう言って。
が何か食事を作ると、いただきますは同時なのに、は憂人が手をつけるまで食べない。
どう?おいしい?期待と不安を込めた幼げな顔に、憂人は飲み込むのもそこそこに、おいしいです、と口をもごもごさせて答える。はよかったと言って、本当に安心したような顔をして、自分もひと口食べて、おいしいねと漏らす。
そういうやり取りもいつか慣れてしまうものだと、心のどこかで思っていたのに。こうして思い出となってしまっても、未だに憂人の心を柔らかく揉む。
己を律することは、憂人にとって苦ではない。住み慣れた家を手放す時でさえ、その後の生活を考慮した上での微々たる面倒臭さくらいしか感じていなくて、管理された生活にも過度のストレスは抱かない。わずかなストレスさえ、テレビ越しに美しい風景やおいしそうな食べ物なんかを見るだけで、簡単に解消されてしまう。憂人はそれだけでも十分、自由を感じられる人間だったからだ。
しかし、といる時はどうだろう。それは、録画された風景なんかじゃなくって、自分の足で気になる場所まで歩いて行って、本当に美しい景色を目の当たりにした時と同じくらいの感動がある。実際は小さなアパートの一室に、これまでとは比べ物にならないほどの、心の自由が生まれた。
けれど、がたばこを吸う自分に近づいてきたとき、抱きしめていいか問いかけてきたとき…憂人は一瞬、その自由が、恐くなってしまったのだ。
の言葉はいつもストレートだ。憂人、愛してるよ。ねえ、ぎゅってしていい?
反面、行動は、言葉に伴わず控えめだ。黙って抱きしめてしまえばいいものを、はいちいち確認する。口先だけとか、軽薄なのでは決してない。たぶんきっと、彼女のトラウマが、そうさせている。
憂人が自分からを抱きしめたのは、何も思いが高ぶったわけじゃない。むしろ、自分をコントロールするためだった。職業柄、よく知っているのだ。欲を解放した人間は、他人を傷つけることもしばしばあると。憂人は裏の人格が何をしでかしているのか、いつも気がかりだ。好き勝手やっているらしいことも、なんとなく知っている。
つまるところ、自分には他人を傷つける、その片鱗がある。
の行動が、自分の思いをぱちんと弾けさせてしまったら。その時もし、万が一にでも、を傷つけてしまったら。──の、かつての恋人のように。
ふたりが出会った当時、には交際相手がいた。情緒の不安定な相手と付き合っていて、精神的苦痛に苛まれ、公園のベンチで声も立てずぽたぽたと涙を流していたに、最初に声をかけたのは憂人ではなく、紫音だった。それを咎めて代わりに話を聞いたのが、との始まりだった。
それはある意味、同情かもしれなかった。苦しみを堪えるように、さも自分が悪いのだというように、声を押し殺して泣くに、憂人は悲しくなった。
根が平和主義者なのもあるだろう。しかし声を上げないと、かき消されてしまうもの、なかったものにされてしまうもの。それが憂人にとっては、獄Luckという形で、身近に感じる感覚だったからかもしれない。
に告白された時、自分は相談役でしかないと思っていたから、憂人はひどく驚いた。付き合い始めてからは、自分はを傷つけまいと心に固く誓った。笑ってほしいと思ったのも、優しくしてやりたいと思ったのも本当だった。
いつしか憂人は、恐ろしくなった。に心が揺さぶられて、時折、感情が自分の制御の手から離れそうになると、こう考えるようになった。
いつか間違って踏み越えて、を傷つけてしまうのではないか。
裏返るまでもなく、ただの自分が。
次の休みはあいにくの曇り空で、憂人は逆に、と話す気持ちが固まってきた。家を出るにしても、荷物はの家にあるのだから、本人と面と向かって話をすべきだ。ただ、うまく話せるかどうか…。
なんでもない風を装い、家に行くと連絡したが、既読がつかない。それが嫌な予兆に思えて、憂人は、いつでも来てと渡されていた合鍵を初めて使った。
「お邪魔します…」
小声で入ると、何やら咳き込んでいる音が聞こえた。
ベランダにの後ろ姿が見えて、まさか病気か何かかと、憂人は慌てて走った。
「!」
こほ、とか弱く咳き込みながら振り返ったから、馴染んだ匂いがふわりと漂った。
衝動的に、の手にあったたばこを取り上げた。
「っ、」心配だった、不安だった。だからといって声を荒げようとした自分に気づいて、憂人ははっと息を詰める。
わかっている、これは境界線だ。灰皿にたばこを押し付ける。
低く深呼吸して、落ち着いて声を発する。
「…こんなもの、吸っては駄目ですよ」
そのとき、弱々しかったの瞳に、初めて、怒りのような光がともった。
「ねえ憂人。私のこと愛してる?」
憂人の、たばこを掴んでいたほうの手が、ぴく、と揺れた。
寸前で押しとどめた気持ちが、喉にせり上がってきて気分が悪い。
「…愛してますよ」
堪えろ。堪えろ。
が、唇を噛んで俯いた。
「……………私のこと、本当は好きじゃない?」
それは、小さな声だった。
ぽろっと、の瞳から涙が零れた。あの頃とは違う、自身の言葉を伴って。
憂人は即座に答えられなかった。本心をむき出しにすることへの躊躇、何より──傷つけまいとしていたが、泣いていたから。
「も、もっとちゃんと、…私を愛してほしいよ…!」
どうしたら愛してくれる?私はどうしたらいいの?泣き叫んでいるに、憂人はどうしたらいいかわからなかった。
には、見透かされていたのだ。こんな自分の臆病さなんて。
ぼろぼろと、憂人の中で何かが崩れていく音がした。律することも不可能なほど、感情が決壊して、音もなくへとなだれていく。
「もうやだ、こんなこと言いたくなかった、ごめんなさい、ごめんね、うぅ」
重みに押し潰されていくように、が泣きじゃくりながらうずくまった。
「……私は、恐いんです」その姿に、なぜだか自分が重なって見えて、憂人はそう口にしていた。
が怯えたように顔を上げる。
憂人は膝をついて、諦めたように微笑んだ。
「私はこれまで、誰かを…こんなにも、愛したことがなかったんです。あなたを愛したせいで、あなたを傷つけてしまったらと思うと」
あんなに謝られたところで、が立てた言葉の爪など、憂人には痛くも痒くもなかった。あんな風に傷つけられるのなら、ずっと私を傷つけていてほしい。そう思ってしまうくらい。
でも、はそんなささいなことさえ、気に病むだろうから。
だから憂人にできることは。
「あなたがあの方にされたことを、私は許しません。…許せない。…それなのに、今の私は、あの人の気持ちを理解してしまいそうな気がして、恐いんです。私は、あなたを傷つけたくない」
だから、と言葉を続けようとした憂人を、が何も言わず、思いっきり抱きしめた。
引っ張られるようにバランスを崩し、憂人はなんとか手をついたものの、かなりに寄りかかってしまっている。
「あの、、」
「いいの」
ややあって、憂人が息を吐き出し、に軽く体重を預ける。重みで、の身体が少し傾いた。だが、は抱きしめる手を弱めるどころか、ぎゅっと強くする。
「いいよ」
がひと言、笑って呟く。
重なり合った互いの心臓は、ばくばくと脈打ち、無秩序にうるさかった。