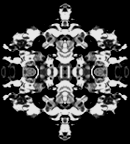 きらきら輝く月の王子と
きらきら輝く月の王子としろくて赤い花の妖精
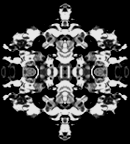 きらきら輝く月の王子と
きらきら輝く月の王子と
しろくて赤い花の妖精
星は銀色、月は金色。
砂漠も金色、白い花。
砂漠はもう夜の12時だった。乳白色の月の光が、シーツの上を照らしている。金色のたてがみの王子は、その上で眠る真っ白な少女を見つめた。
彼女は王子の忠実なるしもべが捧げた供物だった。王子に捧げられる供物はいつも、どこもかしこもエメラルドやルビーのようにぴかぴかしており、大変美しかった。しかし、彼女はいつもの供物とは様子が違った。彼女は、風に揺られる白百合のように、華奢でひっそりとした顔立ちをしていた。
王子は従者を叱りつけるのも忘れて、百合の少女をじっと見つめていた。それからしばらくして、後ろ手に結ばれていた少女の縄を外してやった。
ベッドに腰掛け少女に近寄ると、わずかに胸が上下しているのがうかがえた。その度に、若い娘のみずみずしい香りが星間に漂うようだった。
王子は彼女の瞳を見たい、と思って、けれども起こすのは躊躇われた。彼は深いため息をつき、少女が目覚めるのを待つことにした。
100年の眠りに就いたことのある王子ですら、その夜はとてつもなく長く、終わらないのではないかと感じられた。
王子は、柔らかい頬の彼女のことを、とても好きになった。それは、遠い遠い昔、離れ離れになってしまった恋人に出会ったかのような気持ちだった。不思議と、この少女とは出会うべきだったのだと王子は思った。
白百合が眠りから覚めると、目の前には屈強な、金色の髪を持つ男がいた。
例え彼が王子であったとしても、彼女には人目を忍ぶ獰猛な野獣に見え、声も出ずに思わず後ずさった。かわいそうに、白い顔は大理石のように冷たくなってしまった。
その様子を見た王子は、悲しい瞳をして、しかし黙ったままだった。真っ赤なルビーのような瞳は、妖しさを潜めて、輝きをわずかに失う。
何も言わない男を不思議に思い、少女はそっと問いかけた。
「……あなたは誰?」
「……私は、ディオだ」
彼はそういうと、再び口を貝のように閉じてしまった。しかし少女は、彼の名前を聞いただけでなぜだか懐かしい気持ちになった。彼とは会ったこともないのだと少女は戸惑った。しかしなぜだか少女も、彼とは出会うべきだったのだと感じていた。名前を告げた金色の獰猛な野獣は、もはや1人の美しい、いじらしい青年へと姿を変えた。
少女は花の茎のような細い指先を伸ばして、男の手に触れた。男の冷たい血管がぴくりと動く。
「私は……、私の名前は、。・」
「」
ディオがそう繰り返すと、2人の間にあった糸が結ばれ繋がった気がした。
静かに見詰め合う2人を、大きな丸い月だけが、そっと見ていた。
それからの2人は、まるで離れていた時間を取り戻すように一緒にいた。ディオは長い年月のうちに得た叡智を、まるで御伽噺のようにに聞かせてやった。ディオはたいへん話をするのがうまく、歌でも歌うような美しい声で話すので、はいつまでも聞いていたいと思った。はお礼にと、屋敷から出ないディオに、外の世界がどんなものかを教えてやった。
は日中どんなに元気でも、ディオのたくましい腕を枕にすると、魔法にかかったように安心してすぐに眠ることができた。
ディオのお気に入りは、時折と共に月明かりの元でダンスをすることだった。ディオはダンスを嗜みとしていたから、もちろんその足取りは優雅であった。も、小さな足を軽やかに、くるくると回った。はとても楽しそうに、かわいらしく踊るので、ディオは彼女が花の妖精なのではと思った。
のお気に入りは、ディオの金糸の髪に触れながら、お互いに質問をすることだった。生まれた国、好きな音楽、好きな花――聞けば聞くほど、お互いの魂が強く惹かれていくのが分かった。2人は、こうして出会うべく運命であったのだと気付いていた。ほんの一瞬のすれ違いを、一生のうちに得られぬまま天に昇っていく人々もいる。そう思うと、2人の胸は幸福でいっぱいになり、はちきれそうになるのだった。
ある日いつものようにが質問をした。
「ディオ。あなたの姓は何というの?」
それは何気ない質問であったが、ディオはしばらく黙り込んで、それから木の葉のさざめきのように、「姓は捨てた」と弱弱しく呻いた。その声音に、の胸には北風が吹いたように寂しさが溢れた。
は大きな体躯を縮こめるディオの頭を胸に抱いた。それから、2、3度ディオの金糸を梳いた。
ディオの肩越しには、彼の瞳のような赤い星が輝いている。しかし、の胸中を巣食っていたのは、離れ離れになった彼女の家族のことだった。
家族との旅行の途中、ディオの従者に攫われて、は館にやってきた。今頃は家族もどんなにか心配していると考えると、僅かな焦りが生まれた。
「ディオ、私家族に会いたいわ」
が思わずそういうと、ディオは顔を上げて、苦々しい顔で「……駄目だ」と告げた。
は館からも出られないくらいだからと思って落胆したが、その代わりに別のことを聞こうと思った。
「では、ディオ。私があなたにこうして会えるのは、昼間のちょっぴりの時間と、月が顔を出してから。あなたはいったい、何をしている人なの?」
「俺が恐ろしくなったか」
「いいえ。あなたのことを魂ですら信じている。あなたのことを知りたいだけ」
ディオは質問に答えねばならなかった。ディオはその狡猾さを持ってして、神の前であったとしても嘘をつける自信があった。しかし、の瞳を見つめると、嘘をつくのが彼女への侮辱であり、恥ずべきことであるように感じられた。七色の光が胸のうちを見透かしているような気分になるのだ。ディオはに、嘘がつけなかった。
ディオはいつもそうするように、御伽噺のように自分の野望を語った。はその間1つも目線をそらさずに話を聞いた。
ディオが話し終えて沈黙の帳が下りる。はディオの手のひらを両手で握ると、小さく首を振った。
「ディオ、駄目よ。そんな……人を殺すなんて、恐ろしいこと。今すぐに、やめましょう」
もともと正義感の強いは、強い意志を持った瞳でそう言った。しかし、ディオは困ったように瞳を逸らすだけだった。
「やはり恐いか」
「恐いわ、人を殺すなんてこと……でも、ディオは恐くない。血なら私がいくらでもあげる、ディオが望むだけ。だから、やめてちょうだい。そんなことをしてほしくないのよ」
ディオは黙って、の背中を掻き抱いた。それは柔らかな拒否であった。砂漠の紫色の風が、温いままの頬を撫でる。
ディオには強い、運命とも呼べる意志があった。抱きしめる指の先から、ディオの不変の意志を感じて、は銀色の涙を流した。張り裂けそうなほどの痛みが、2人の胸を蝕んでいた。
どうして出会ってしまったのか。は考える。ディオのことが嫌いなのではない。攫われたことも、愛を享受することに比べれば瑣末に思えた。しかし、出会った時の歓びは、今や蜃気楼のように、おぼつかないものとなっていた。
正義の陽の下に生きる者と、悪の闇を従える者。2人は全く逆の道を見つめたまま、互いの魂の伴侶に出会ってしまったのだ。
あの夜から、2人の間ではディオの野望について話されることはなくなった。
言葉は少なくなったが、暖かさを分け合う動物のように身を寄せ合うようになった。しかし相手の身体に触れれば触れるほど、重苦しい胸の痛みを2人は覚えた。眠っている間だけ、2人は現実の世界ではない、運命から解放された、どこか遠くへと旅立てた。そこにはお互いしかおらず、美しい花が咲いていて、2人でためらいもなく太陽の下を歩けるのだ。
このまま時が止まれば、とは何度も思った。しかし幾度となく日が昇り、ディオの話していた「ジョースター一行」が日に日に近づく足音が聞こえてくるようだった。
ある夜、2人でダンスを踊っていると、ディオがそっと動きを止め、それからの頬を優しく撫でた。つららのような指先で、の心は凪いだ。
「ディオ、どうしたの」
「何でもないさ」
ディオは笑ってそう言うと、手品のように赤い薔薇を一輪ぱっと出して、に差し出した。
棘も抜かれた薔薇は、天鵞絨のように美しい。月の光に照らされた赤薔薇は、孤高の美しさを放っている。
「百合のほうがよかったか」
「いいえ、とっても綺麗。ディオみたい」
一瞬落ち込んでいたことも忘れて、は無邪気に顔をほころばせた。その様子に、ディオは少しだけ寂しい顔をした。
それから強くを抱きしめて、耳元で囁いた。
「、君は運命の人だ。もしオレが人間であったなら、あの太陽の下で共に歩いてみたかった」
ディオはとうの昔に鍵をかけた記憶を掘り起こし、太陽を思い描いた。金色の陽の光を浴びるは、どんなに生き生きと呼吸をして美しいことか。考えるだけで、ディオは幸せな気分になった。
「……でも、ディオがもし人間だったら、私達は巡り逢うことができなかったわ」
「ああ、そうだろうとも」
ディオはそっとの身体を離した。はなぜだか、嫌な予感がしていた。ただ、身体はかちこちに強張るだけで、2人の身体はそっと離れた。
ディオの大きな掌が伸び、の瞳を隠す。の瞼はそっと下がると、そのまま全身から力が抜けた。
「おやすみ。そして、さよなら、」
がはっとして目を覚ますと、そこはどこかのホテルの上であった。慌てて身を起こすと、胸の上に置かれていた封筒がはらりと落ちた。
赤い封蝋のされた封筒からは、がいつも眠るときにする、ディオの甘い香りがした。
封筒の中には、いくらかの紙幣と、簡素な手紙が同封されていた。手紙にはやはり美しい筆記体で、簡単な目覚めの挨拶と、同封されたお金で国へ帰るよう記されていた。それから思い出したように、困ったときには自分の友人を尋ねるようにと、連絡先が走り書きされていた。
の胸を、暗雲が覆った。間違いない、「ジョースター一行」は、もうディオの元へたどり着いたのだ。
ダイヤモンドのように硬い正義が、ディオを打ち砕くのか、それともディオが、彼らを打ち砕くのか。は結末がわかっているように思えた。
靴はなかったが、そのままホテルを飛び出した。ここはいったいどこなのか、そんなことは気にせずに、は自身の直感を信じて走った。なぜなら、ディオとは目には見えない運命の糸で結ばれているからだ。たとえどこにいようとも、にはディオの存在が感じられた。
足をもつれさせながら、半ば引きずるようにはディオを探し求めた。人がまばらになり街を抜けていたが、は自身の勘を信じた。空は紫色にきらめき、支配者である太陽が少しずつ顔をのぞかせていた。
「ディオは、どこ……」
がくがくと震える足を叱咤しながら、はきょろきょろと辺りを見回した。
すると、の近くにワゴンカーが止まり、運転手が降りてきた。
「君、ここは危ないから離れなさい! 何をしてるんだ」
「でも、私……」
運転手がの肩を掴んでそう言った。は戸惑ったが、ワゴンカーから出てきた担架に思わず目をやった。
その瞬間、の心臓は凍ったように冷たくなり、頭が真っ白になった。
担架は乱暴に横向きにされ、寝かされていたものが、砂っぽい地面に落とされる。
見覚えのある金色の靴、いつも共に眠っていた魔法の腕。
運転手の制止も振り切って、はその死体の側に膝をついて縋り付いた。身体の表面についた血液が、僅かにの頬をよごした。
その時のの頭の中には、正義も何もなかった。ただ、愛する魂を失ったことだけが、彼女の心を満たしていた。
運転手に言われた承太郎とジョセフが、慌てて車を降りてきた。しかし、少しだけ顔を上げた彼女の頬を、黄金の涙が次々に伝っていくのを見て、ジョセフは今にも駆けださんとする承太郎の肩を掴んだ。
黄金の光が大地に満ちて全てのものが息吹を吹き返す。しかしディオの身体は、の頬に付いた血でさえも、一瞬で砂に変わり、風に流れてきらきらと輝きながらどこかへ消えてしまった。
には聞こえる気がした。風の中を漂う、ディオのいとおしい声が、優しく自分の名前を呼んで愛を囁いているのを。そう思うと、風が優しく彼女の髪をさらった。
砂埃にまみれた腕輪を拾い上げて、は祈るように瞳を閉じ、そっと口付けをした。
それから承太郎達を振り返り、小さくお辞儀をした。ジョセフも喪に服すような表情で頭を下げた。
は歩き出した。帰ろう、自分の家へ。そう思った。もうここにはディオはいない。いるのはディオに染められた自分だけ。
ディオと共にダンスを踊った小さな足の裏は、土にまみれてぼろぼろだった。それでも、は痛みを感じなかった。
胸の痛みも感じなかった。絶望なのか、希望なのか、今のには分からなかったが、全てが抜け落ちたように真っ白だった。
太陽の下で、ディオと過ごした月夜のことを思い出した。それだけでの瞳からは涙が溢れた。はジョセフ達に背を向けて歩きながら、たくさんの涙を零した。
それから、顔を上げて太陽を見た。眩しい光が、の濡れた瞳をきらきらと照らす。
「さようなら……ディオ」
星は銀色、月は金色。
太陽は黄色。赤い花。